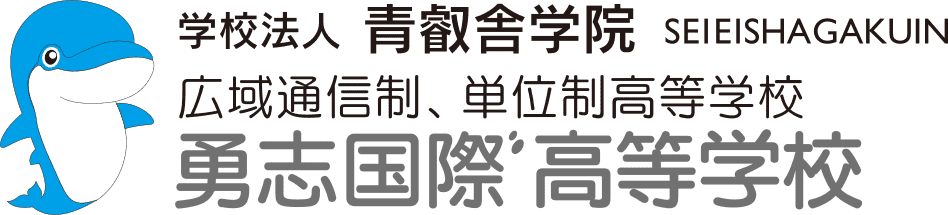今回は、日本文明が独自の価値を持つ一大文明であることを百年以上も前にいち早く見抜いた西洋人、小泉八雲(パトリック・ラフカディオ・ハーン)を紹介します。
パトリック・ラフカディオ・ハーンは、1850年、当時イギリス領であったイオニア海に位置するレフカダ島に生まれました。ラフカディオというミドルネームは、レフカダ島からとられたものです。ハーンが6歳の時、両親が離婚し、父親に引き取られましたが、父親の再婚によりハーンはアイルランドのダブリンにいる親戚に預けられました。
不幸は続き、16歳の時、寄宿学校で回転ブランコで遊んでいる最中にロープの結び目が左目に当たって怪我をし、失明してしまいます。それ以降、左目を隠すように左を向いたポーズで写真に写るようになりました。
19歳の時、ハーンはアメリカに渡ります。新聞記者として働きながら、文芸記事も書くようになり、次第に名前が知られるようになりました。のちに作家として働くことになる基礎はこの時期につくられました。
ハーンは明治23(1890)年に来日しました。はるばる日本に来たのは、日本についての本を書くためでした。ハーンは、日本に暮らしているような、日本人の思考で考えているような、そういう印象を与える本を書きたいと思っていました。ハーンは翌年、小泉節子と結婚し、帰化して小泉八雲と名乗りました。「八雲」の名前は、一時期住んでいた島根県の旧国名である出雲国にかかる枕詞「八雲立つ」にちなんだものとされています。また、帰化したのは、遺産が妻や子に確かに渡るようにということを考えてのこととも言われています。
八雲は怪談がたいへん好きで、耳なし芳一の話などをまとめた『怪談』という作品を出しています。それを八雲に教えたのは夫人の節子でした。八雲は節子の怪談をとても気に入り、「本を見る、いけません。ただあなたの話、あなたの言葉、あなたの考えでなければいけません」と言い、怪談を自分のものとして話すように要求しました。節子はそのせいで夢にまで見るようになりましたが、節子が自分のものにした怪談は鬼気迫るもので、八雲は恐怖にとりつかれたように震え上がりました。八雲がそのようにうち震えたものだけが自身の作品となったのです。
八雲は、怪談以外にも日本を深く愛し、日本人の心に世界のどこにもない美しさを見いだし、数々の名作を書きました。八雲が最も驚いたことの一つに、日本人の微笑がありました。日本人は楽しいにつけ悲しいにつけ、いかなる時も微笑みます。西洋人にはそれが分からず、不誠実、偽善あるいは侮蔑に見えることがありましたが、八雲は探求の末ついに八雲なりの考えを持つに至ります。「日本人の微笑は長い年月をかけて丹念に作り上げた礼儀作法の一つであり、それはまた沈黙の言語」であり、「礼儀正しさの極の自己否定に至った笑い」であるということです。日本人の微笑の奥にある心は「他人に対する細やかな思いやりと自己抑制」というふうにも述べています。
西洋人の自己中心的生き方の対極にあるのが日本人本来のこうした生き方であり、八雲はこれに深く感動しました。「私この小泉八雲、日本人よりも本当の日本を愛する」と愛妻に語った八雲は、美しい日本と日本人の心に魂をうち振るわせた西洋人だったのです。