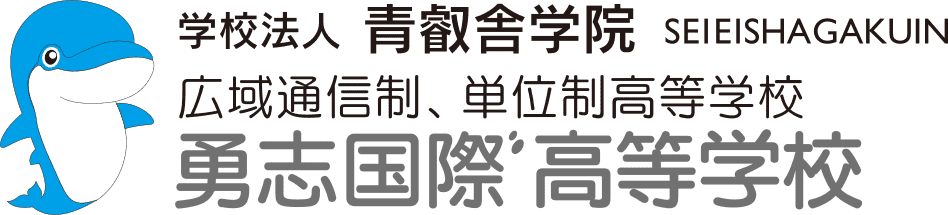今回は、明治時代初期に外交官として手腕を発揮した人物、副島種臣(そえじま たねおみ)を紹介します。
副島種臣は、文政11(1828)年9月9日、父の枝吉忠左衛門種彰と母喜勢の次男として、佐賀に生まれました。父は藩校弘道館の教諭であり、兄の経種は、楠木正成公の尊皇精神を学ぶことを目的とした「楠公義祭同盟」を組織している人物でした。父と兄の影響を強く受けて副島は育ちました。少年時代から藩校弘道館で学び、嘉永5(1852)年には藩命により京都に留学し、皇学を研究しました。安政6(1859)年には藩校の教諭に抜擢されました。
その後、長崎で英学修行を行った副島は、明治政府の参議となり、法典編纂に携わります。その後は外交問題を担当するようになりました。明治4(1871)年には、第3代外務卿(現在の外務大臣に当たる)に任命され、条約改正交渉にも取り組んでいきました。
明治5(1872)年6月、南米ペルーの汽船マリア・ルーズ号が横浜の船体修理のために入港しました。この時、船いっぱいに詰め込まれていたのは、奴隷(苦力(クーリー))にされた清国(現在の中国)の人たちでした。
碇泊中、清国人の木慶が海に飛び込んでマリア・ルーズ号を脱出し、港内に同じく碇泊していたイギリス軍艦に泳ぎ着いて助けを求めました。話を聞いた英国人士官は、英国公使ワトソンに連絡しました。脱走人は横浜の英国領事館の手をへて、神奈川県庁に引き渡されましたが、マリア・ルーズ号の船長は、木慶の返還を要求しました。船中にいる清国人は移民であり、彼らを虐待したことはないと主張しました。
当時、日本は欧米列強と通商条約を結んでおり、相手国に「治外法権」を認めていました。日本に在住する外国人が犯罪をおかした場合、日本側はこれを裁判する権限を持っていないということです。列強の治外法権下にある日本が、ペルーと清国の間の紛争に干渉する資格があるのか、自信がなかったため、県庁の担当者は、木慶を返してしまいました。
日本側の処置に満足しないワトソン公使が、マリア・ルーズ号が奴隷船でないかどうか確かめに行くと、木慶は懲罰を受け、半死半生の目に遭っていました。ワトソンはこの状態を副島に報告し、船長を再審問すべきことを勧告しました。
副島は、「ペルーは治外法権を日本において持っていない。日本国は、自国の主権によってこの事件を処理しなければならない。これは国際法上、合法である」と考え、奴隷となっていた清国人は解放されました。これがひとつのきっかけとなり、マカオでの奴隷売買は消滅しました。また、この対応の結果、日本は清国から感謝されたばかりではなく、イギリスの信用も得て、条約改正に向けて大きく前進することができました。
明治12(1879)年4月、副島は侍講に就任し、明治天皇と昭憲皇后にご進講を行うようになりました。さらに明治25(1892)年には内務大臣に就任するなど、政府の中枢を支えました。
明治30年代に入ると、持病の悪化に伴い、さまざまな会合を欠席することが多くなりました。そんな中、日露戦争で旅順陥落の知らせを受けた副島は嬉しさのあまり筆をとって漢詩を記しました。これが副島の絶筆となりました。明治38(1905)年1月30日に副島種臣は78年の生涯を終えました。
副島種臣の生涯を見てみると、外交官に最も必要なものは、幼少期からの「日本人」としてのプライドであるように思います。ぜひ、みなさんの中から、外交官として日本を背負ってくれる人物が出ることを期待しています。