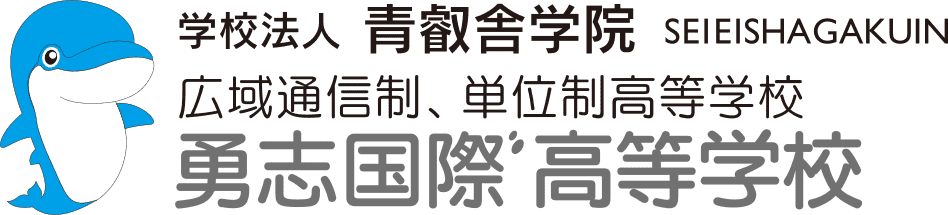福岡学習センターのある福岡市は、以前からアジア各国との交流があり、現在も街中ではいろいろな言語を耳にします。今回は、福岡で育ち、アジアに目を向け、各国の独立への動きを手助けした頭山満を紹介します。
頭山満は、安政2(1855)年4月12日、福岡城下の西新町(現在の福岡市早良区西新)に、武士の筒井亀策とイソの三男として生まれ、幼名を乙次郎といいました。のちにイソの実家の頭山家を継ぐために養子となり、頭山姓を名乗ります。少年時代はわんぱく者の反面、小さいころから記憶力が強く、講談を聞きに行った際には、帰ってからその文句や登場人物の名前をことごとく覚えていたほどでした。
西南戦争が終わって2年後の明治12(1879)年暮れ、頭山は西郷隆盛の家を訪ねました。留守を預かっていた、陽明学者の川口雪蓬(せっぽう)は「西郷はもう亡くなった」と言って追い返そうとしましたが、頭山は「西郷先生の身体は死んでも、その精神は死なぬ。私は西郷先生の精神に会いに来た」と食い下がり、西郷の愛読書を福岡へ持ち帰ったそうです。
その年、頭山は政社組織「玄洋社」の立ち上げに参画します。玄洋社の気風は、「頭山がやるというならおれもやる。貴様も来い、お前も来い、という純粋な精神の集まりだった」と評されています。この玄洋社から出た人物には、日露戦争当時に諜報活動で活躍した明石元次郎、総理大臣になった廣田弘毅などもいました。
明治30(1897)年、頭山は後に辛亥革命を成し遂げる孫文と会い、「救国愛民の革命の志は熱烈なものであった」と後に語っています。当時の孫文は最初の蜂起に失敗し、日本に亡命していました。欧米列強の植民地となっている状態から抜け出さなくてはならないという思いを感じた頭山は、孫文を支援しました。
大正4(1915)年、インド独立を目指して立ち上がったものの、失敗し日本に逃れてきたラス・ビハリ・ボースにも頭山は救いの手を差し伸べました。「インド独立に奔走している志士を敵の手に渡して殺させることは、情においても、国の体面にかけても、断じて許せない」と、ボースをかくまうことを決心します。ボースを頭山に紹介したのは、同じく頭山に助けられた孫文によるものでした。
頭山は、日ごろ新宿の中村屋でパンや菓子を買い、そこの主人の相馬愛蔵とも顔なじみになっていました。その日も、中村屋の店へ立ち寄ると、相馬は新聞を見て、日本政府のイギリスに対する弱腰に憤慨しているところでした。万一の場合には、ここへかくまってもいいと言います。頭山は、さっそく計画を実行にうつしました。まずボースほか1名は自動車に乗せられ、麻布の頭山邸に運ばれました。尾行してきた警官数名は入口で見張っています。中に入った二人は、すぐ服を着替えて裏の断崖を下り、坂下へ出ました。そこから用意の自動車で新宿中村屋へ向かいました。邸内では、仲間の宮崎滔天らが、頭にターバンを巻いてインド人に見せ、刑事の注意をひきつけました。中村屋に着いて自動車を降りると、待ち構えていた店員2人がボースらの脱いだ外套と帽子を身につけ、行方をくらましました。逃亡に成功したボースはインド独立のために奔走しました。ボースは独立を見ることなくこの世を去りましたが、その2年後にインドはイギリスからの独立を果たしました。中村屋のインド式カリーは、その際にボースが伝えたものです。
昭和19(1944)年10月4日、頭山満は89年の生涯を終えました。「おれの一生は大風の吹いたあとのようなもの。何も残らん」と語った通り、頭山の生家は今はなく、残したお金もありませんでした。頭山は玄洋社の若い人間に向け、「ひとりでいても淋しくない人間になれ」と言っていました。一人ひとりが光を放つ存在になれ、という意味で言っていたということです。頭山自身が、玄洋社という一人でも戦う勇気のある純粋な人間の集まりを作ったゆえの言葉だったのでしょう