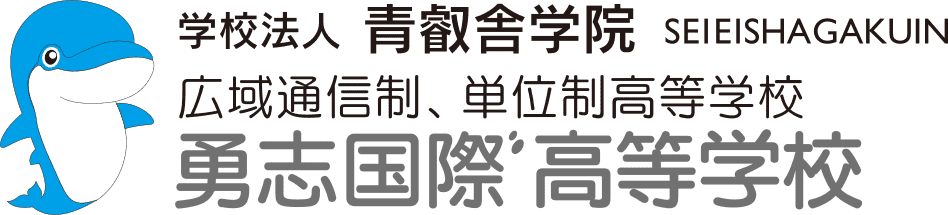今回は、日清戦争の講和条約、「下関条約」を締結した際の外務大臣、陸奥宗光を紹介します。
陸奥宗光は、紀州藩士であった父・宗広と母・政子の六男として、天保15(1844)年8月20日に生まれました。宗弘が藩内の抗争に敗れて失脚した際、子供ながらにそれを聞いた宗光は、虎のように荒れ狂い、床の間にあった刀を抜いて表に飛び出そうとしたほどでした。その様子を見た、ある本屋の主人が、「紀州家に仇討ちをされるなら、天領の代官になりなさい。」と言ったところ、宗光は喜んで、当時代官の教科書とされた『地方凡例録』や『落穂集』を勉強しました。のちに宗光は地租改正を提案するのですが、それにはこのときの素養があったからだと言われています。
宗光は、父・宗広と親交のあった坂本竜馬に見込まれ、文久3(1863)年、勝海舟の海軍操練所に入りました。宗光は勝海舟の教えを受け、坂本竜馬に「二本刀を差さなくても食っていけるのは、俺と陸奥だけだ」と言われるほどになります。明治維新に当たっても、税制改革の考えが採用され、大蔵省の地租改正事務局長に就任して新政府の財政の基礎を築き、現在でも財務省の毎年の最大の事業である、予算書作成の作業を初めて完成させたのも宗光でした。
陸奥宗光は、明治10(1877)年の西南戦争勃発後、藩閥政府を倒すべく画策しますが、これが知られて逮捕され、東北の監獄に5年間収監されます。出獄後は伊藤博文の勧めもあり、アメリカとイギリス、オーストリアのウィーンで8年間勉強に集中しました。この経験が、後の陸奥に大きな影響を与えました。
陸奥が力を注いだうちの1つは、開国期に欧米と結んでいた不平等条約の改正でした。明治26(1893)年12月、イギリスとの交渉でまとめた改正条約案は立派な平等条約でしたが、議会では野党から外国人の日本での活動に関して懸念される意見が出されました。それに対して陸奥は、暗に清(中国)の例を出し、外国人に対して臆病でありながら、虚勢を張って外国とのトラブルになった例は少なくないと指摘した上で、「今日の外交の要務は、自尊自重、何人をも侮らず、何人をも怖れず、文明強国の仲間入りをすることであります」と演説で論じました。時の英国臨時代理公使は、陸奥に書簡で「貴下の演説は、貴政府の進歩的政策が誠心誠意のものであることを十分主張することができよう」と書き送っています。
明治27(1894)年、日清戦争が勃発します。明治28(1895)年に陸奥が著した『蹇蹇録(けんけんろく)』は、日清戦争についての陸奥の回想録であり、当時の様子が具体的に描かれています。開戦前の日清それぞれの朝鮮に対する考え方、陸奥と伊藤博文との開戦直前のやりとり、下関条約締結に至る内容まで書かれ、その後の三国干渉で遼東半島を手放さなければならなくなる過程まで詳細に記してあります。
陸奥が『蹇蹇録』を執筆した理由について、「そもそも余が本編を起草する目的は、昨年朝鮮の内乱以来延(ひ)いて征清の役に及び、竟(つい)に三国干渉の事あるに至るの間、紛糾複雑を極めたる外交の顚(てん)末(まつ)を概叙(がいじょ)し、以て多年の遺(い)忘(ぼう)に備えんと欲するのみ(そもそも『蹇蹇録』を起草する目的は、昨年、朝鮮の内乱以後、清国との戦いとなり、最後には三国干渉を受けたまでの間、紛糾し複雑を極めた外交の顚末を述べることで外交の備忘録にしようと思ったからである)」と書いています。また、最終段には、「畢(ひっ)竟(きょう)我にありてはその進むを得べき道に進み、その止まらざるを得ざる所に止まりたるものなり。余は当時何人を以てこの局に当らしむるもまた決して他策なかりしを信ぜんと欲す(つまり、日本は行けるところまで行き、とどまるべきところにとどまったのであって、自分としては、誰がこの場に当たっても、これ以上の策はなかったと思う)」とあります。まさに全エネルギーを注いで外交に取り組み、その記録を後世に残したのでした。
『蹇蹇録』完成後、1年余りで陸奥宗光は逝去しました。まさに大きな仕事を成し遂げた外交官でした。