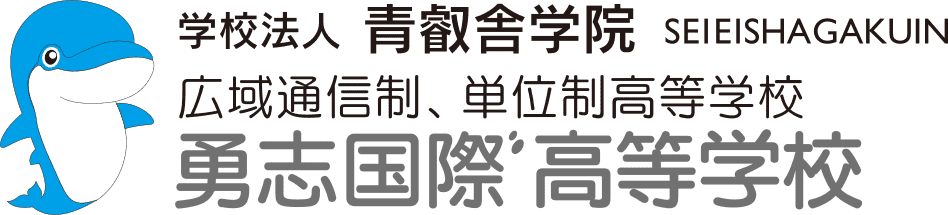今回は、明治期に活躍し、以前に紹介した秋山真之の親しい友人でもあった、正岡子規を紹介します。
正岡子規(常規)は、慶応3(1867)年10月14日、伊予国温泉郡藤原新町(現在の愛媛県松山市花園町)に、松山藩士正岡常尚、八重の長男として生まれました。明治5(1872)年、幼くして父が没したために家督を相続し、母方の大原家と叔父の後見を受けました。外祖父の私塾に通って漢書の素読を習い、漢詩や戯作、軍談、書画などにも親しみ、小学校では友人と回覧雑誌を作り、試作会を開きました。
明治13(1880)年、旧制愛媛一中(現・松山東高校)に入学しますが、明治16(1883)年、同校を中退して上京し、受験勉強のために共立学校(現・開成高校)に入り、翌年、旧藩主家の給費生となり、秋山真之とともに東大予備門(のち第一高等学校、現・東大教養学部)に入学しました。しかし、真之は経済的な理由により海軍兵学校に進むことを決めます。一方の子規は明治23(1890)年、帝国大学(現・東大)哲学科に進学したものの、後に文学に興味を持ち、翌年には国文科に転科しました。明治24(1891)年頃からは先人たちの膨大な数の俳句を読み、自ら「子規」と号して句作を行っています。夏目漱石もまた、子規の誘いを受けて句作に取り組みました。
子規は、俳句以外でも興味を持ったことに何にでも取り組みました。18歳頃からは野球に熱中し、「打者」「走者」「四球」「飛球」などの言葉を用いたのは子規が初めてであったとされています。また、幼少期のなまえが升(のぼる)であったことにかけて、「野(の)球(ぼーる)」という別名を用い、「久方の アメリカ人の 初めにし ベースボールは 見れどあかぬかも」など、野球を題材にした俳句や短歌を詠んでいます。
大学を中退した子規は、政治評論家の陸羯(くがかつ)南(なん)のもとで明治25(1892)年に新聞『日本』の記者となります。明治28(1895)年4月には結核を病んでいた状態のままで、日清戦争の従軍記者として自ら志願しました。従軍の前には、命を落とすことも覚悟し、俳句の弟子であった高浜虚子(きょし)・河東碧(へき)梧(ご)桐(とう)に決死の思いを示す長文の手紙を書き送っています。結果的に、一か月間に及ぶ酷寒の地での従軍生活が体に害を及ぼし、脊椎カリエスという激痛を伴う病気と闘うことになってしまいました。
その中でも、子規は創作活動を続けました。明治30(1897)年には俳句雑誌『ホトトギス』を創刊し、俳句分類や与謝蕪村を研究し、俳句の世界に大きく貢献しました。短歌においても『歌よみに与ふる書』を新聞『日本』に10回にわたって連載しました。そこでは「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候」と、紀貫之と『古今和歌集』を激しく攻撃しました。反論の投書に対しても紙上で反論するとともに、同書の中で善き歌、悪き歌の例を挙げて具体的に評しました。
子規は、自分が武士の子どもであるということに誇りを持ち続けていました。武士道に人一倍強い憧れを抱き、「武士道における覚悟とは何か」を、自問自答し続けていました。そしてある日、子規が得た結論は、「武士道における覚悟とは、いついかなる時でも平然と死ねることだ」ということでした。しかし、重病を患い、痛みに苦しむ中で、本当の覚悟を悟ります。「どんなに苦しくても、どんなに痛くても、生かされている『いま』を平然と生きることこそが本当の覚悟だ」と。その死生観があったからこそ、病床においても精力的な文筆活動ができたのです。
正岡子規は、明治35(1902)年9月19日の未明、家族や親しい者たちに看取られ、34歳という若さでこの世を去りました。子規が臨終の時まで肌身離さず持っていたのは、親友・秋山真之から贈られた毛布だったと言われています。子規が詠んだ俳句は約24,000句、短歌は2,500首に及びました。