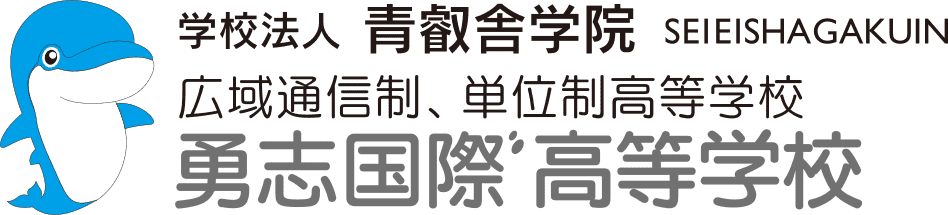今回紹介するのは、小説『坂の上の雲』でも描かれた、「日本騎兵の父」として知られている秋山好古を紹介したいと思います。
秋山好古は、安政6(1859)年1月7日、松山藩士秋山久敬、貞子の三男として生まれ、はじめは信三郎と名づけられました。早生児で生まれたために虚弱な体質でしたが、育つにつれ大柄になりました。弟の真之が生まれた時、秋山家の家計は火の車で、父が「生まれた子は寺へでもやらんと育てられん」と話していたのを聞いた好古は、「お父さん、赤ん坊をお寺へやっちゃいやぞな、うちが勉強してな、お豆腐ほどの(厚さの)お金をこしらえてあげるがな」と訴えました。この一言で、真之が寺へ預けられることはまぬがれたそうです。
家計が苦しかったこともあり、独学ではありましたが、好古は勉学に励みました。近くの風呂屋で働きながら、わずかに得たお金で書物を買い、読んでいました。明治7(1874)年、好古は小学校教員の検定試験を受けるために大阪へ向かいます。検定試験を受けて合格した後、さらに正教員の資格試験があると聞き、これも合格して教鞭をとることになりました。さらに翌年、年齢をごまかして大阪師範学校を受験し、これも合格します。当時は師範学校に通うだけで月給が支給されており、いくらかは松山に仕送りをしたそうです。
師範学校卒業後に愛知県の小学校で教員として働いていた折、陸軍士官学校の受験を勧められました。試験を受けたのは200人ほどで、合格したのは37人でした。入学に当たり、歩兵、砲兵、騎兵、工兵の4つの兵科を選択する際に、好古は「騎兵科にします」と答えました。ここから、「日本騎兵の父」が誕生したのです。明治初期の日本では、騎兵の用法すら知らないのが実態でした。好古の同期として入学した者のうち、騎兵科はわずか3人でした。明治12(1879)年12月23日、好古は陸軍士官学校騎兵科を卒業し、21歳にして陸軍騎兵少尉となりました。
好古は陸軍士官学校騎兵科教官、陸軍大学校を経て、フランスへ留学した後に明治27(1894)年に勃発した日清戦争に参戦します。好古が率いる部隊は「秋山支隊」と呼ばれ、敵の砲台の位置、陣営の地形などの敵情探索に当たりました。終戦後は、陸軍乗馬学校の校長となります。ロシアとの戦いに備え、学生たちにナポレオン戦争などの際のロシア軍の慣用戦法を研究させました。日露戦争の前年には、シベリアで行われたロシア軍の大演習を参観しました。ロシア側としては、ロシア軍にとうてい勝てないと思わせる意図がありましたが、好古の感想は、「ロシア陸軍は恐れるに足らないが、馬鹿にはできない」というものでした。それからほどなくして日露戦争が始まります。
秋山好古が率いる騎兵第一旅団は、奥保鞏(おくやすかた)の第二軍の元に組み込まれ、日清戦争と同様、敵軍偵察をしつつ、敵を防ぐのが主な役割でした。遼陽会戦では、ロシア側指令官クロパトキンのいる司令部、弾薬庫、食糧貯蔵庫に向けて砲撃を行うなど、陽動作戦も行いました。沙河会戦、黒溝台会戦では、世界最強と言われたロシアのコサック騎兵との戦闘に果敢に挑み、退却させました。最後の決戦となった奉天会戦では、乃木希典率いる第三軍の先鋒として奉天の北方へ進出する役目を負って攻め込み、ロシア軍に動揺させて勝利に貢献しました。
好古は、当時連合艦隊の参謀であった真之にこのような手紙を送っています。「兄弟共に未曾有(みぞう)の国難に斃(たお)るるを得ば一生の快事と今後の舞台を相(あい)楽(たのしみ)居り候」好古は、「未曾有の国難」に立ち向かい、倒れたとしても「一生の快事」と考えていました。軍人として、秋山家を背負う者としての気概を背負っていました。
「人間は一生涯働くものだ。死ぬまで働け。」と後輩によく話していた好古は、予備役に退いた後も、亡くなる半年前まで中学校の校長として職務を全うしました。昭和5(1930)年11月4日、日露戦争の夢を見ていたのか、「奉天の右翼へ…」等のうわ言を続けた後、72年の生涯を終えました。