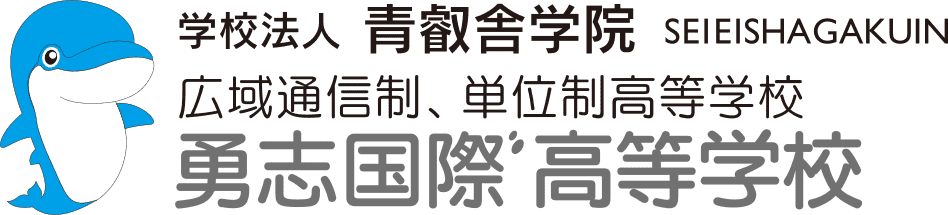今回は、「日本の細菌学の父」と呼ばれた、北里柴三郎を紹介します。
北里柴三郎は、嘉永5(1853)年1月29日、現在の熊本県小国町に生まれました。少年時代は腕白で、将来は軍人になることを希望していましたが、父母の願いにより、藩校時習館から熊本医学校に学び、そこでお雇い外国人のマンスフェルトに出会ったことがきっかけで、本格的に医学への道を志しました。
明治8(1875)年、東京医学校(現在の東京大学医学部)に入学しました。しかし、成績は芳しくなく、8年後の明治16(1883)年、32歳でようやく医学士となりました。医学は単に個人の病気を治すためだけのものでなく、貧困や衛生環境など社会的問題にも取り組んでいく必要があると考えた柴三郎は、高給の地方病院長の職を断り、内務省の衛生局に勤めました。
明治18(1885)年、柴三郎は同郷で同期生の医学者、緒方正規に細菌学の手ほどきを受け、長崎に流行したコレラの研究で初めて成果を上げることができました。これを契機に、柴三郎はドイツに留学します。留学先のベルリン大学では細菌学の研究に明け暮れ、朝、目覚めたらまっすぐ研究室へ行き、一日が終わるとまっすぐ自分の部屋へ戻るという生活を1年余りも続けました。
4年後の明治22(1889)年、柴三郎が歩んだ一本道に、花が咲きました。当時の細菌学の権威たちが挑戦し、ことごとく失敗に終わっていた破傷風菌の純粋培養に、医学後進国の一留学生、北里柴三郎が成功したのです。さらに、その菌体の毒素を少しずつ増量しながら動物に注射し、血清中に抗体を生み出すという画期的な血清療法を開発しました。この功績に対し、ドイツ政府も柴三郎にプロフェッソル(大博士)の称号を贈りました。その後、イギリスのケンブリッジ大学からも「細菌学研究所を創設するので、所長に就任して欲しい」という依頼が舞い込みましたが、それを断り、最終的に選んだ道は、日本に戻ることでした。柴三郎は、当時の日本の脆弱な医療体制を改善し、伝染病から日本国民を守りたいという志に燃えていたのです。
しかし、日本政府には予算がなく、日本に伝染病研究所を設立したいという柴三郎の希望を聞き入れず、内務省への復職も許されませんでした。そこに救いの手を差し伸べた人物がいます。現在も一万円札の肖像でおなじみの福沢諭吉です。諭吉は柴三郎を高く評価していたため、研究の場を無償で提供することを即決し、私財を投じて港区芝公園に研究所を建てました。そうして設立されたのが『伝染病研究所』でした。柴三郎はその所長となり、明治27(1894)年にはペスト菌の発見という歴史上に残る業績を上げました。後継者教育にも力を注ぎ、赤痢菌を発見した志賀潔、野口英世などを世に送り出しました。
また、福沢諭吉への恩返しも忘れてはいませんでした。諭吉が慶応義塾に新設することになった医学部の教授陣に、志賀潔をはじめ、ハブの血清療法で有名な北島多一など、研究所の名だたる教授陣を惜しげもなく送り込みました。自らも医学部の学部長として10年余りの間無報酬で働き、恩義に報いました。
北里柴三郎の弟子であった志賀潔は、自著の中でこう記しています。「私は大学を出たばかりの若造だったから、(北里柴三郎)先生の共同研究者というよりも、むしろ研究助手というのが本当であった。しかるに研究が予期以上の成果をあげて論文を発表するに当たり、先生はただ前書きを書かれただけで、私一人の名前で書くように言われた。普通ならば当然連名で発表されるところである。発見の手柄を若造の助手一人に譲って恬然(平然)としておられた先生を、私はまことに有り難きものと思うのである。」
北里柴三郎が常々口にしていた、「事を処してパイオニアたれ。人に交わって恩を思え。そして叡えい智ちをもって実学の人として、不ふ撓とう不ふ屈くつの精神を貫け。」という言葉は、現在も北里大学の建学の精神「開拓」「報恩」「叡智と実践」「不撓不屈」という形で残っています。これからも北里柴三郎が残した、日本人研究者としてのDNAは引き継がれていくことでしょう。その一人は勇志生の中の誰かかもしれません。