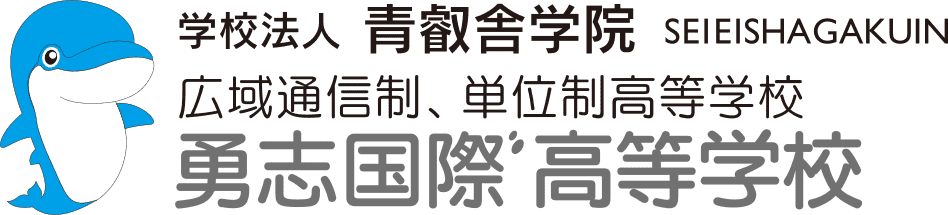今回は、誰もが知っている、世界に誇るタイヤメーカー「ブリヂストン」の創業者、石橋正二郎を紹介します。
石橋正二郎は、明治22(1889)年2月1日、「嶋屋」という仕立物屋を営む石橋徳次郎とマツの次男として福岡県久留米市に生まれました。高等小学校3年から久留米商業学校(現在の久留米商業高校)に進学し、後の基礎を学びました。わずか17歳で家業を継ぎますが、大きな改革を早速行います。当時は、商人は「丁稚(でっち)」として小さい頃に修行に出されることが多く、休みは少なく、給料も盆と年の暮れに小遣い銭を与えるぐらいでした。そんな中、正二郎は、丁稚に給料を払い、休みも与えるようにしました。また、扱う商品を、着物やシャツから足袋一本に絞ることにしました。父の徳次郎はこれらをやめるよう諫めましたが、この正二郎の決断が後の発展に繋がります。そして、正二郎は読みやすい「志まや」に屋号を替えました。これは、当時足袋の製造でトップを走っていた「つちや」に対抗したものです。宣伝方法でも、自動車での宣伝方法を考え、九州初上陸の自動車で「志まやたび」の看板を両サイドに取り付け、のぼりを立てて九州全土へ宣伝して回りました。
社名を「日本足袋」とした頃、販売不振に苦しんでいた正二郎は次の手を考えます。この頃はまだ靴がなく、わらじが中心でしたが、耐久性に難がありました。そこで考えついたのが、足袋の底にゴムを張ったもので、現在も商品として残る「地下足袋」でした。地下足袋は特に鉱山労働者に重宝されました。その頃、関東大震災が東京を襲いますが、その復興にも足を守る地下足袋が求められました。地下足袋が普及したことで、日本の新しい履物文化が作り出されていったのです。
昭和5(1930)年2月、正二郎は、近い将来、日本でも自動車が普及し、自動車タイヤの需要が高まると考え、国産の自動車タイヤの生産を始めることを社内に発表しました。当時、自動車のほとんどは外国車で、数少ない国産車ですらほとんどのタイヤは欧米からの輸入品でした。そのため、正二郎がタイヤ業界に参入するためには大変な苦労を強いられましたが、正二郎は、これからの日本の自動車の発展に貢献するという国家的使命感が強く、また、自らの手で新産業を創るという開拓者精神から、自動車タイヤの国産化を決意しました。タイヤに刻む商標は、苗字の石橋からとり、「BRIDGESTONE」(ブリッヂストン)としました。最初は不良タイヤが多く、「ブリッヂストンは三年待たずにパンクするばい」と揶揄されていましたが、品質の向上により昭和7(1932)年、ブリッヂストンタイヤが商工省優良国産品に認定されるとその年に14,000本のタイヤを海外に輸出し、海外進出を果たしました。
そんな中、戦時中の昭和17(1942)年4月、インドネシアのバイテンゾルグにあるグッドイヤー社の工場を委託経営するよう命が下ります。正二郎は、「もし日本がこの戦争に負けて皆さんが帰国する場合、工場は完全な姿のままグッドイヤー社に返して欲しい。それが日本人の心です。」と訓示しました。その後、終戦後の昭和24(1949)年4月、バイデンゾルグ工場の支配人が正二郎を訪れました。それは、工場の設備が磨き上げられ、メンテナンスして返されたことへのお礼と、グッドイヤー社との提携の提案のためでした。正二郎、そして派遣された社員たちの誠意はしっかり伝わっていたのです。
晩年の頃、ソニー会長の井深大が石橋正二郎を見舞った際、ゴルフの話になりました。井深は、「スライス(ボールが曲がること)はどうして起こるのか」と疑問を抱き、ドライバーやボールまで分析をした際、ブリヂストンのボールはレントゲンで見ると芯が曲がっていることを石橋に伝えました。井深が帰ると、石橋はすぐに病室にゴルフボールの担当責任者を呼び、真っ直ぐ飛ぶ最高のボールを開発するよう厳命したそうです。
石橋正二郎は、会社経営を通しての理想社会を目指した人物でした。「事業を拓くは、世のため、人々のために」という事業哲学を持っていました。そして、何より新しいことに挑戦する「チャレンジ精神」があったからこそ、現在のブリヂストンに石橋正二郎の精神が引き継がれ、世界一のタイヤメーカーになったのでしょう。