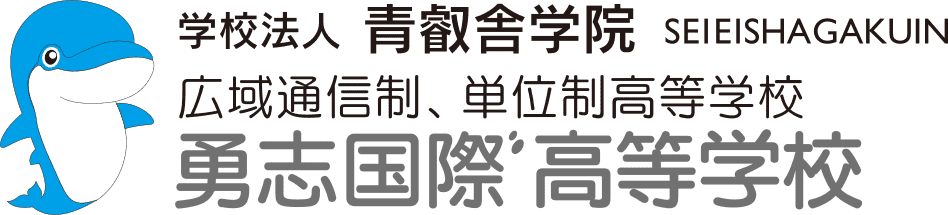今回は、現在の千円札に肖像画が描かれ、医者として世界各地で活躍した野口英世を紹介します。
野口英世は、幼少の頃の名前を清作といいました。明治9(1876)年、福島県猪苗代町の貧しい農家に生まれた清作は、満1歳半の時に囲炉裏に落ち、左手に大やけどを負います。しかも、医者に見せることができなかったため、親指と中指がこぶしに癒着し、他の指も内側に曲がったままになってしまいました。「手ん棒」というあだ名をつけられましたが、それにも負けず、努力を重ねました。左手が不自由なままでは農業を継ぐこともできないため、母・シカの勧めで猛勉強しましたが、現在の中学校に当たる高等小学校に進むためには、高い学費が問題でした。そんな中、高等小学校の小林栄先生は、「清作くんほど優秀な生徒が、このままではもったいない。」と、学費を出すことを申し出ました。試験には清作も合格し、当時の子供のうち5%ほどしか入学できない高等小学校に進学できました。ここでは、先生や同級生の助けによって募金されたお金で左手の手術を受け、何とか動かせるまでに回復しました。清作は主治医であった渡部鼎かなえに弟子入りを志願し、医師になることを決意します。
当時、清作は、医院の薬局方で働きながら、国が行う試験の勉強をしていました。「ナポレオンは1日に3時間しか眠らなかった」と言いながら、本当に睡眠時間3時間で日々を過ごしました。清作は明治29(1896)年に上京し、満19歳で医学前期試験に合格します。その後、歯科医である血脇守之助のもとに身を寄せ、済生学舎(現在の日本医科大学)に通い、満20歳で後期試験に合格し、医師としての第一歩を踏み出しました。
明治31(1898)年、清作は、北里柴三郎が所長を務める伝染病研究所の助手となります。その頃、名前を英世と改名しました。そこで、英世には大きな出会いがありました。英語が得意であった英世は、アメリカの医学者、フレスキナー博士の案内と通訳を任されたのです。英世は、この出会いからアメリカへの留学を考えるようになりました。さらに、その資金のために入った検疫所の仕事で、英世は伝染病の細菌であるペスト菌を発見し、関係者の間で有名な存在になりました。
明治33(1900)年、ついに英世はアメリカに渡ります。アメリカではフレスキナー博士、ミッチェル博士の指導のもと、最初に行ったヘビの研究が評価され、ペンシルベニア大学の助手に任命されました。さらに、1年間デンマークで留学した後、アメリカで最初の本格的な研究所である、ニューヨークのロックフェラー医学研究所で研究を始めました。英世は梅毒の研究を進め、その原因となる細菌のスピロヘータ・バリダの純粋培養に成功し、世界にその名が知れ渡りました。
大正7(1918)年からは、黄熱病の研究を開始します。当時、エクアドルで流行していた黄熱病の調査に渡り、ワクチンによって黄熱病は治まったかに思われました。しかし、英世が発見したとされた病原体は、黄熱病に良く似た病原菌でした。その後、英世はアフリカのガーナに渡り、黄熱病の研究を続けましたが、英世自身が黄熱病にかかってしまいました。野口英世は、「わたしには、わからない。」という言葉を残し、昭和4(1929)年、この世を去りました。後に分かったことですが、黄熱病の病原体は、細菌よりも小さなウィルスだったために、当時使われていた光学顕微鏡では見ることができなかったのです。後に電子顕微鏡によって、ようやく観察できるようになりました。
野口英世の命をかけた働きは、現在でも世界各国で深く感謝されています。エクアドルでは、1976年に生誕100年を祝い、「ヒデヨ・ノグチ」学校の生徒の手で、胸像が除幕されました。また、ペルーでもヒデヨ・ノグチ学園があり、この2つの学校は、福島県にある、野口英世の母校と今も交流しているそうです。
世界で活躍した野口英世は、自宅の机の上の地球儀を、いつも日本が見える位置に置いていたといいます。それは、離れていても家族、郷土の猪苗代、そして祖国日本を思う心からではないでしょうか。