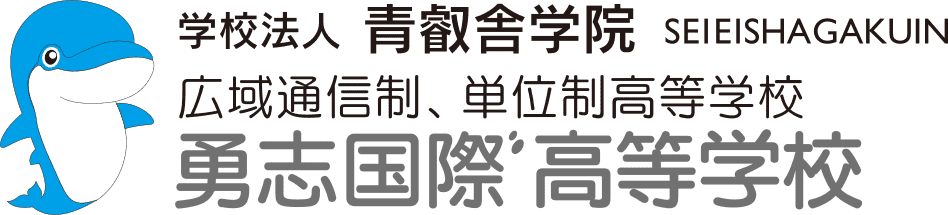毎年、年末になると日本のいたるところで聞かれる、ベートーベンの「第九」こと、第九交響曲。特に皆さんが耳にする「歓喜の歌」は、非常に有名な楽曲です。実は、この曲の日本での初演は、東京でもなく、大阪でもなく、四国の徳島でした。徳島県の板東(現在の鳴門市大麻町)に収容されていたドイツ軍俘虜によって、大正7(1918)年6月1日に演奏されたのです。その収容所の所長であったのは、松江豊寿(まつえ とよひさ)という会津(福島県)出身の軍人でした。
大正3(1914)年から始まった第1次世界大戦において、日本はイギリスとの日英同盟に基づいて連合国側に加わり、ドイツに宣戦布告をして青島のドイツ要塞を攻撃しました。降伏したドイツ軍から日本に送られた俘虜は約4,600人、そのうち約1,000人が板東俘虜収容所に収容されました。
ここで、「俘虜」とは、敵兵を幽閉、拘禁して収容所に入れておいた状態をいいます。なぜ、俘虜が板東で「第九」の演奏を行ったのでしょうか。
松江は最初の日に、俘虜にこう訓示しました。「諸君は祖国を遠く離れた孤立無縁の青島において、最後まで勇敢に戦った兵士である。しかし、利あらず日本軍に降伏したのである。それゆえに私は諸君の立場に同情を禁じえない。諸君は自らの名誉を汚すことなく行動してほしい。私の考えは博愛と人道の精神と武士の情けをもって、諸君に接することである。諸君もこのことを理解し、秩序ある行動をとってほしい。」ドイツ人の俘虜にとって「武士の情け」に接するのは初めての機会だったことでしょう。しかし、敗者を思いやる武士道精神はしっかり俘虜たちに伝わりました。松江は、会津武士特有の、「ならぬものはならぬ」「弱者はいたわるべし」という倫理観を持って俘虜に接しました。
また、松江の板東収容所だけでなく、日本の収容所では、俘虜の扱いに関する国際条約「ハーグ協定」を遵守しました。例えば、労働については「国家は将校以外の俘虜に、その階級や技能に応じた労働につかせることができるが、その労働は激しいものであってはならない」としています。日本は、この規定を忠実に守り、俘虜に接しました。
板東収容所は、俘虜たちから「模範収容所」と呼ばれていました。なぜなら、一定の秩序のもと、よく組織され、生産労働はもとより、文化活動、社会事業、地域との交流なども許されていたからです。ドイツ人の俘虜は、「われわれの収容所は小さな町に似ている。小さな砦にも似ている。」と、当時の収容所の新聞『ティ・バラッケ』に書いています。また、もともと、この時期の日本人はドイツ人俘虜を憎む気持ちはあまりなく、「珍しい人たちが来た」という印象が強かったようです。地域との交流という観点では、多彩な職歴を持つドイツ人俘虜から、第九を代表する音楽をはじめとして、洋菓子製造、ウイスキー製造、野菜栽培、養豚など多岐にわたっての技術指導が行われました。これも松江の計らいでした。
民間の交流は一時途切れたものの、昭和35(1960)年に『徳島新聞』に掲載された記事をきっかけに現在まで続いています。ドイツでは収容所生活を懐かしみ「バンドー会」が作られています。また、昭和48(1973)年には鳴門市と西ドイツのリューネブルク市が姉妹都市の関係を結びました。その後の昭和57(1982)年には鳴門市民会館が落成し、そのこけら落としで演奏されたのは、ベートーベンの「第九」でした。
収容期間を終えたドイツ人俘虜に、松江はこう挨拶しています。「諸君、解放おめでとう。この日を諸君は長い間、一日千秋の思いで待ってきたのである。諸君の喜びを思い、私もうれしい。…お別れに当たり諸君の健康とご多幸を祈り、長年、ご苦労でしたと申し上げ、私のごときものの命令指示を、よくここまで厳守されたことに感謝する。」最後まで会津武士としての倫理観を捨てることなく、ドイツ人に尊敬された松江豊寿の人間性がこの言葉に表れています。