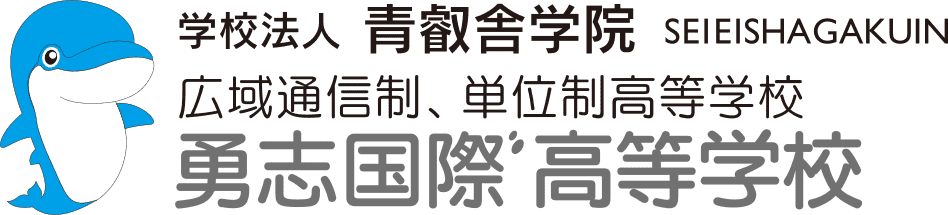今回は、前回まで紹介した吉田松陰の下で学び、松陰の亡き後に塾生を束ねた久坂玄瑞を紹介します。
久坂玄瑞は、藩医である久坂良迪(よしみち)の子として、天保11(1840)年に生まれました。13歳の時、母の富子、兄の玄機、父の良迪が続けて亡くなり、天涯孤独の身となります。当時、跡を継いで医者になるのが嫌で、明倫館で学んでいました。しかし、そこでの学問に飽き足らず、父の亡き後にいろいろと助けてくれた宮部鼎蔵(ていぞう)から吉田松陰の話を聞き、松陰に手紙を書きました。まだ若く、血気盛んな玄瑞は、「日本に勝手にやってきて、無礼を働く米国の使者は切るべし」と過激な意見を吐いていました。これに対し、松陰は「思慮が浅く、至誠から出た言葉ではない。僕はこの種の文、この種の人を深く憎む」と厳しく叱責しました。しかし、この時の玄瑞は納得せず、さらに反論を書きました。そこで松陰は突き放すように「承知した。貴君がそこまで自説を曲げぬなら、断然実行して、米国の使者を切られよ」と返事を書きました。玄瑞はそこでようやく目が覚め、自分の発言には命を賭してでも責任を持たねばならないことを思い知り、直ちに松下村塾に入門しました。
入門の翌年には、松陰の妹・文と結婚し、杉家に同居しました。松陰の期待と信頼の厚さがうかがえます。松陰は、文に宛てて、「久坂玄瑞は、防長(長州藩)年少第一流の人物にして、もとよりまた天下の英才なり」と立派な青年であることを認識させ、妻としての道を説きました。
そんな中、大老・井伊直弼の安政の大獄において、松陰は死罪を言い渡されます。その際、次の言葉が残されました。
「君たちは僕の志をよく知っているはずだ。だから、僕の死を悲しむ必要はない。その死を悲しむことは、僕を知ることに及ばない。どうか、僕の志を継いで、大きく伸ばしてほしい」
この言葉を受け、吉田松陰の亡き後、玄瑞は松陰の遺志を引き継ぎ、松下村塾の面々をまとめ上げました。文久元年(1861年)12月、玄瑞は、松下村塾生を中心とした長州志士の結束を深め、みんなで分担して珍しい本などを写し、それを売って同志に何かあった時のために使えるようにしようと、桂小五郎、高杉晋作、伊藤俊輔(博文)、山縣有朋ら24名の参加者で一(いっ)灯(とう)銭(せん)申(もうし)合(あわせ)を創りました。ちょうどその頃から玄瑞と各藩の志士たちと交流が活発となり、特に長州、水戸、薩摩、土佐の四藩による尊皇攘夷派同盟の結成に向けて尽力し、玄瑞は尊王攘夷運動、反幕運動の中心人物となりつつありました。
ちょうどその頃、長州藩は、朝廷(公)の伝統的権威と、幕府及び諸藩(武)を結びつけて幕藩体制の再編強化をはかろうとした公武合体という政策を打ち出しつつありました。これに危機感を持った玄瑞は、各地の攘夷派志士と協力して行動し、文久2(1861)年に藩主の毛利敬親に、通商条約を破棄して和親条約まで引き戻すことを主張した『廻(かい)瀾(らん)條(じょう)議(ぎ)』を上堤しました。敬親はそれを受け入れ、以後はそれをもとに長州藩は動いていきました。
しかし、翌年に起こった公武合体派のクーデター、八月十八日の政変により、状況は一変します。尊王攘夷派の公家が追放され、会津・薩摩が実権を握るようになりました。さらに、池田屋事件で長州藩は、松下村塾で学んだ吉田稔麿ら多くの志士たちを失います。それを知った長州藩の人間は激怒し、戦の支度を整え、京都に向かって進撃を始めました。玄瑞はそれを止めることができず、戦いに赴くことになりました。これを禁門の変といいます。この戦いで、久坂玄瑞は25歳の若さで生涯を閉じました。
明治維新の後、西郷隆盛は、木戸孝允(桂小五郎)に対してこう言ったそうです。
「もし久坂先生が生きておれば、互いに参議などと言ってふんぞり返っていることはできぬな」
それだけの人物が25歳でこの世を去ったことは残念なことでしたが、さらに久坂玄瑞の気持ちは受けつがれ、明治維新が成し遂げられたのでした。