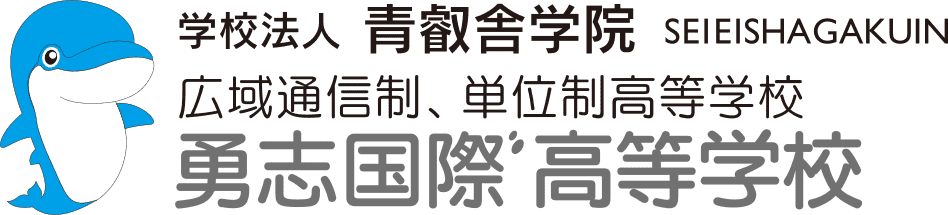~国を愛する心を育むために~
世界の指導者が語る大東亜戦争の真実(アメリカ編その1)
18歳から有権者つまり主権者となる皆さんのためのコーナーを今年度も続けていきます。主権者の心構えで最も重要なのは、「国を愛する心」だということをすでに学びました。それは主権者が自分の国を愛することは最も自然なことですし、国を愛する主権者がいてこそ、その国は発展することができるからです。国を愛する主権者が選ぶ代表者は当然愛国心を持った人物になります。国を愛していない人が主権者を代表して政治をやれば、国は滅びてしまいます。
国を愛するということは、国の歴史や国柄を理解するということでもあります。我が国の場合、そのために避けて通れない関門があります。それは大東亜戦争(太平洋戦争)を正しく理解するという課題です。
昭和16年(1941年)12月8日から昭和20年(1945年)8月15日ポツダム宣言の受諾までの間、日本は大東亜戦争(太平洋戦争)を戦いました。そして敗れました。なぜ日本はこのような悲惨な戦いをしたのでしょうか。
戦後は、日本が一方的に戦争を仕掛けてアジア各国を侵略して、アジア諸国をはじめ世界の国々に甚大な被害と迷惑をかけたという歴史観がまかり通ってきました。
この「侵略の歴史観」の通りだとするならば、「国を愛しなさい」と言われても、納得はできないと思います。愛国心はおろか日本人であることの誇りも持てなくなってしまいます。ですから、その歴史観が正しいのか否かを検証することは愛国心を培う上で極めて重要な作業です。
今月号から複数回にわたって、世界のリーダーや識者が、大東亜戦争(太平洋戦争)を、どのように見ているのか、公表されているその言葉を紹介することで、客観的に検証を試みたいと思います。
【アメリカ】
最初はアメリカです。大東亜戦争で日本が戦ったのはアメリカをはじめ西洋の国々でした。そしてアメリカに敗れました。そのアメリカのリーダーだった人や、アメリカを代表する識者は、この戦争をどのように見ていたのでしょうか。今回はフーバー元大統領です。
◎ハーバート・フーバー(第31代大統領)
彼は、1929年から1933年まで第31代のアメリカ大統領だった人物です。1941年から大東亜戦争がはじまりましたから、開戦前のアメリカの指導者です。フーバー大統領の次に第32代大統領となったのが、フランクリン・ルーズベルトです。彼の大統領の任期は、1933年3月4日から1945年4月12日、4期目の途中で急死するまで12年間の長期に及びました。つまり大東亜戦争(太平洋戦争)の際のアメリカの大統領です。終戦直前に急死し、副大統領だったトルーマンが第33代大統領に就任しました。
ルーズベルトの前任の大統領だった、フーバーが、その回想録の中で述べている次の言葉は、戦後の大東亜戦争の見方を根本的にひっくり返すほど重要な意味を持っているといわなければなりません。
「私は、①ダグラス・マッカーサー大将と、1946年5月4日の夕方に3時間、5日の夕方に1時間、そして6日の朝に1時間、サシで話をした。私が、日本との戦争のすべてが、戦争に入りたいという狂人(ルーズベルト第32代大統領)の欲望であったと述べたところ、マッカーサーも同意して、また、②1941年7月の金融制裁は、挑発的であったばかりでなく、その制裁が解除されなければ、殺戮と破壊以外のすべての戦争行為を実行するものであり、いかなる国といえども、品格を重んじる国であれば、我慢できることでなかったと述べた。
ルーズベルトが犯した壮大な誤りは、1941年7月、つまり、③スターリンとの隠然たる同盟関係となったその1か月後に、日本に対して全面的な経済制裁をおこなったことである。④その経済制裁は、弾こそ撃っていなかったが本質的には戦争であった。ルーズベルトは、⑤自分の腹心の部下からも再三にわたって、その挑発をすれば遅かれ早かれ、日本が報復のための戦争を引き起こすことになると警告を受けていた。」
①のダグラス・マッカーサー大将というのは、日本敗戦後の日本を占領統治した連合国軍の最高司令官のことです。
1946年(昭和21年)、フーバーは占領下の日本を視察しましたが、その時に東京でマッカ-サーと会談しています。そのときのことを回想したのがこの文章です。
二人が会談した1946年の5月4日は、極東国際軍事裁判(東京裁判)が開廷された翌日のことです。この東京裁判で、大東亜戦争終結までの日本の昭和史が裁かれ、日本の一方的な侵略だったとされて、A級戦犯7人の絞首刑が確定しました。戦後日本の侵略史観は、この東京裁判でつくられたのです。これを東京裁判史観といいます。
このフーバー証言で、東京裁判の主宰者であったマッカーサーが、開廷時点ですでに日米戦争を挑発したのはアメリカであって日本ではなかった、つまり、大東亜戦争は日本の侵略戦争ではなかったと考えていたという驚くべき事実が述べられています。
東京裁判が、国際法を踏みにじり、近代法の基本も無視し、開廷前から結論ありきの裁判に名を借りたリンチ劇だったことは、今や世界の常識になっています。
「日本は侵略国家だった」とする「東京裁判史観」を創った張本人が、その裁判が予定していた結論を、裁判が始まる時点で否定していたということは、東京裁判の判決は、極東国際軍事裁判所のねつ造であったということを意味します。このことの重要性は、計り知れないものがあるといわなければなりません。
②の金融制裁というのは、1941年7月25日の、米国による在米日本資産凍結、そしてこれに続く対日石油全面禁輸のことです。
日本は、当時、石油の95%を輸入に頼っていました。そしてその輸入先はアメリカでした。石油の全面禁輸は、日本に死ねと言うに等しいことでした。
それでも日本は対米交渉で平和的に道を開こうと、必死の努力を継続しました。
しかし、ルーズベルト大統領は、その交渉に応じる考えはなく、いかにして日本側から対米戦争を始めさせるかのみを考えていたと、チャールズ・A・ビーアド博士(アメリカを代表する歴史・政治学者)は、その著書「ルーズベルトの責任」で明らかにしています。
③の「スターリンと隠然たる同盟関係となった…」の意味は、1941年3月成立した「レンドリース法」(武器貸与法)で、終戦までに、中国、イギリス、ソビエト連邦(1991年12月崩壊し現在はロシア)、フランスなどに総額501億ドル(現在の価値に換算して7000億ドル以上)に及ぶ大量の戦闘機や武器、軍需物資の供与をしましたが、そのことだと思われます。ソ連のスターリンに対して、総額の22.6%に及ぶ113億ドル(現在価値約1600億ドル)を供与しています。
ソ連は、日本と相互不可侵条約を結んでいましたが、終戦間際になって、突如一方的にその条約を破って日本に参戦しましたが、ルーズベルトとの同盟関係がその前提にあったということです。
④の「その経済制裁は、弾こそ撃っていなかったが本質的には戦争であった」という表現は、大統領経験者のフーバーの感覚では、ルーズベルトの一連の対日経済制裁の中でも、とりわけ先述した在米日本資産凍結と石油の全面禁輸が、宣戦布告なしの実質的な戦争行為と映ったということです。
⑤の腹心の部下とは、スターク海軍作戦部長のことを指すと思われます。彼はルーズベルト大統領から対日石油禁輸について意見を求められて
「禁輸は日本のマレー、蘭印(ベトナム)フィリピンに対する攻撃を誘発し、直ちに米国を戦争に巻き込む結果になる」
と警告していました。
フーバーは、ルーズベルトがこれらの腹心たちの警告を無視して日本を戦争に挑発していったことを痛烈に批判しているのです。